 十月号(H29)
十月号(H29) 十月号(H29)
十月号(H29)下り簗

ひきしまる山の容チよ下り簗 中村若沙
落鮎になほ簗といふ関所あり 清水忠彦
夏の間川の中流域で成長した鮎は、秋になる頃、産卵場となる川の下流へと徐々に下りて来る。その鮎の習性を利用して捕獲するのが下り簗。川を下ってゆく鮎は落鮎とも呼ばれ、秋の季題である。やがて産卵場に辿り着いた鮎は砂場に卵を産みつけた後、大半は死んでしまう。卵から孵化した幼鮎は河口や沿岸周辺で越冬。翌年若鮎となって遡上を始める。

近江の国は古来より琵琶湖の恵によって支えられてきた。
えり漁、おいさで漁そして簗漁など多彩な漁法が今に伝わっている。安曇川の簗漁の起源は千年以上前に遡る。平安時代には京都の上賀茂神社の御厨(みくりや)となり、ビワマス、アメノウオ、鮎、鯉などを献上したという記録が残っている。《御厨》とは神様へのお供え物、神饌を献じる重要な役割を担っていた神領(じんりょう)のこと。現在でも五月の葵祭には上賀茂神社に干し鮎が、十月にはアメノウオが献上されている。

春生じ、夏長じ、秋衰え、冬死す、故に《年魚》とも名づけられ、川の藻を食べ、よき香がするので《香魚》とも呼ばれる鮎。錆鮎、渋鮎とも名づけられる秋の鮎。万緑の中なる上り簗は見に行ったことがあるが、紅葉はじまるころの一味違う下り簗にも一度行ってみたいものである。

至夏さんにふと会へさうな苑晩夏 長﨑佳子

加藤あやの寸評
平成二十九年六月一日、五十嵐至夏様御逝去。合掌。
高木石子先生から、つけていただいた「至夏」の俳号で大病のあとも、芦屋ホトトギス句会、未央神戸句会、そして例会と必ず出席されて、消え入りさうな声ではありましたが、凛としたお名乗りが懐かしく、思い出されます。
あれから三ヶ月余、その至夏さんに会えそうな気がしたというのです。亡き人を偲ぶ思いが去りゆく夏に託されました。
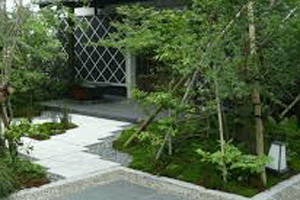
朽船や水夫の匂ひの草いきれ 中本 宙

加藤あやの寸評
未央七月吟行は浜寺公園でした。戦前までは大阪随一の海水浴場で、歌枕としても名高い高師浜でもあります。戦後は一時、米軍に接収されてもいました。時代の流れにより埋立てられて、今は水路を隔て工業都市に変貌、しかし、立派な松林は残され、市民の憩いの公園となり親しまれています。その一角にはまなしの咲く砂場が設えてあり、一艘の捨舟があります。その草深い中に水夫の働いていた昔が甦り、「水夫の匂い」という措辞になりました。


この句に初めて出会ったとき虚子に何事があったのだろうかという気持ちを抱かせました。状況は虚子に師事する大橋仙男の招きにより仙男山荘に泊まった時に虚子は高齢もあって座敷にて、ついうとうととしてしまいました。その時の恥ずかしい気持ちや仙男に申し訳ない心の内をさらりと一句にまとめています。ここで私が気になったのが「生かなし」の文字です。かなしとは哀し、悲し、愛し、等色々な意味合いを含んでいます。
身体の衰えを自然の流れとして自分を許す心、それはつまり他人愛にも通じるのですが、ここで私が特に感じ取ったのは虚子独特の感覚、つまり自然の中の自分として描いているのではないか、ということです。
虚子には禅の心を極めたような句が見られますが、かと言って宗教に浸ったり座禅を組んだりの修業は無かったとあります。宗教から一歩離れるという意味ではなく、虚子はもっと生命の根源的なものを感じとっていたのではないか。つまり宗教を超えたもっと自然の本質を悟っていたように思えます。

いくら悟りを開いても人間は生きんがために動植物の殺生をせねばならない。
「大悪人虚子」と自分自身を言わしめたのはその辺のことを表現したかったのではなかったのか…。
私は父の放蕩が原因で体に問題を抱えてこの世に生を受けましたが、世界を見ると人間の愚かさによる悲劇が山とあります、これも生かなしなのだろうか…。
虚子ならどのように答えるのだろうか?宗教を超えた自然の根源を悟った感のある虚子であればこそ、極楽の文学の境地に至ったのであろうと思います。
しかし、我々凡人は現実的に生きていかねばならないとも思っていて、虚子の境地に至らないと、単なる変人としか世間は受け取らないと思うのであります。

高木石子の一句鑑賞-句集「顕花」-

上方の女房ぶりなる菊人形 石子
大阪枚方市では二〇〇五年まで九十六年間「大菊人形展」が開催されてきた。
毎年テーマを決め展示される菊人形はそれは見事であり、浮世絵の世界をテーマにした年もあり、作者も見物に行かれたのであろう。
明るく一家を切り盛りする浪速女房の菊人形が鮮やかに蘇る一句である。

Copyright(c)2017biohAllRightsReserved.