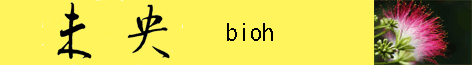 七月号(H28)
七月号(H28)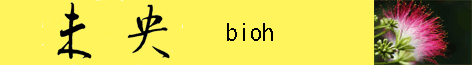 七月号(H28)
七月号(H28)後の祭り

《後の祭り》とは、時機を逸して後悔の念を表す言葉。所謂手遅れのこと。この後の祭りの語源には、大きく分けて二説あるとされている。
京都八坂神社の祇園祭は七月一日から約一か月間行われる。そのうち山鉾と呼ばれる豪華な山車が繰り出される十七日の山鉾巡行を《前の祭り》と呼び、二十四日にある還車の行事を《後の祭り》と呼ぶ。後の祭りは山鉾も出ず、賑やかさがなく、見物に行っても意味がないことから、手遅れの意味になったとする説。もう一説は、葬式や法事など、故人の霊を祀ること。亡くなった後に盛大な儀式をしても、本人には分らず仕方がないことから、後悔の念や手遅れの意味に使われるようになったとするものである。一般的には祇園祭の説が有力とされているが、どちらもありそうな説である。

それに似た慣用句もある。《六日の菖蒲》と《十日の菊》。六日の菖蒲は五月五日の節句の翌日の菖蒲のこと。十日の菊は、九月九日の菊の節句の翌日の菊のこと。いずれも時機に遅れて役に立たないもののたとえとされている。

何れにしても旬を大切にする日本人らしい慣用句ではないかと思われる。泉州の水茄子、京の鱧料理などの食材が美味しくなる頃。俳人は殊更この旬にこだわって暮らして行きたいもの。旬のものをいただき、生き生きとした旬の俳句を作ってゆきたく思う。

昼闌ける残花の里に人を見ず 長尾美代子

加藤あやの寸評
故里の原風景のような、静かな里山の残花の景、と思う一方で、静まり返った昼を思う時、迫っている過疎化という現実を、後に見るような複雑な思いの生れます。
姉さん被りの農婦らが集う、お昼やお喋りを楽しむ景のほしいような気もします。「人を見ず」がちょっと淋しい。

子雀の行く先々に光生れ 小野一泉

加藤あやの寸評
雀の子を詠む時、描写に使う言葉は、散る、啄む、飛び跳ねる等、いろいろありますが、作者は、光が生れると描写しました。そこが新鮮な佳句となったのではないでしょうか。


細見綾子は明治四十年、当時の氷上郡芦田村で生を受け、県立柏原高女卒業後、NHK朝ドラで人気を博した「あさが来た」のあさのモデルとなった広岡浅子が創立に尽力した日本女子大学を卒業。同時に許嫁と結婚したが、夫は二年後に病死し、失意のうちに帰郷。まもなく母が病で去り本人も肋膜炎を病んでしまった。往診に来てくれていた医師で俳人の田村青斎に勧められ俳句の道に入り、その後松瀬青々の薫陶を受ける。「俳人の大和路」という本の中で掲句に出会いその平明さに心を惹かれました。原稿を依頼され三十数年振りに秋篠寺を訪れました。晩春といえ寒の戻りで底冷えのする中、大和西大寺で下車、先づは大茶盛で有名な西大寺を参拝し徒歩で向かう。綾子が通った同じ道であろうか、今は店舗や住宅が建ち並び、畔焼きをするような田畑は見当らない。やがて門前に三反程の田を右に見て境内へ。この田で畔焼きをやっていたのだろうか。ビロードを敷きつめたような素晴しい苔庭を通り国宝の本堂へ。二組の夫婦連らしき人がおられるだけの静かなお堂で、三十数年振りにお会いする伎藝天像は、やさしい眼差しでお迎下さいました。

「女身仏に春剥落のつづきをり」と綾子が詠んだように今尚剥落が続いているのだろうか。やさしさと色気の満ち溢れた像が、永遠に保たれることを願わずにおれません。多くの高名な俳人が、この地を訪れ名句を数多く遺しているが、今の時代にはどのような句を作るのか、想像するだけで楽しくなる。朝日カルチャー中の島教室で俳句を始め十二年になりました。未だ五句の提出句を作るのに四苦八苦しております。
自分のペースでのんびりと趣味の一つとして続けて参りたいと思います。

高木石子の一句鑑賞 −句集「顕花」−

落したる団扇ふまるる祭かな 高木石子
祇園祭に行かれたのであろうか。あまりの人波に使っていた団扇を落してしまい、拾おうとするのだが、下駄や靴に踏まれ、なかなか拾うことができない。 しかしこれも又、祇園囃子の音色と共に、夏祭の記憶の一部として懐かしく思い出されるのである。

Copyright(c)2016biohAllRightsReserved.