 二月号(H31)
二月号(H31) 二月号(H31)
二月号(H31)国栖奏(くずそう)
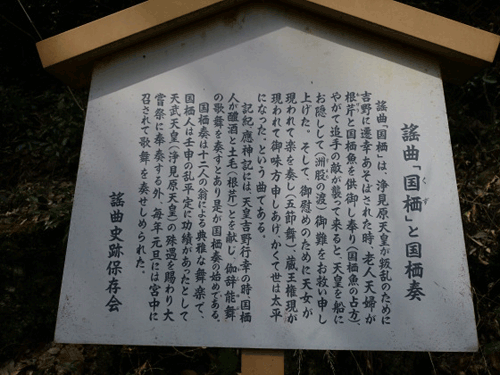
国栖奏は古代部族であった国栖人の歌舞。応神天皇の吉野行幸の時に歌舞を奉納したと記紀に書かれている。吉野町南国栖浄見原(きよみはら)神社で陰暦一月十四日に国栖の人によって歌舞が現在でも奉納され、県の無形民俗文化財に指定されている。神前には山菓(栗)、醴酒(一夜酒)、赤腹の魚(ウグイ)、土毛(根芹)、毛瀰(赤蛙)などが供えられる。この赤蛙は吉野地方の貴重な蛋白源であったらしく、吉野の山奥での最高のもてなしの珍品であったと考えられる。

壬申の乱に大海人皇子(おおあまのおうじ)が吉野で兵を挙げたとき、国栖人が酒や魚を差し上げて奏上し、戦勝を祈願したといわれる。勝利を得た大海人皇子は天武天皇となり、国栖人のこの歌舞を「翁の舞」と名付けて以来、朝廷の行事には国栖奏が演じられるようになったといわれる。国栖舞の宮中参内は絶えたが、今も受け継がれて、浄見原神社にて毎年演じられている。

切り立った断崖の細い道を、古代衣装の烏帽子一行が拝殿に向かって静かに進む姿は、千三百年の昔にタイムスリップしたようで、華麗な宮中絵巻を見るようである。長い歴史を秘めた土地柄を感じさせる国栖奏、是非一度は見ておきたい行事である。

岩襖もて世をへだて国栖の奏 石倉啓輔
衣冠つけその顔となる国栖翁 奥村八千代

この角に多佳子住みなし辻小春 吉田敦子

松田吉上の寸評
橋本多佳子は昭和四年、小倉市から大阪市帝塚山(現住吉区)へ転居し、昭和十九年までここに住んだ。作者はその多佳子旧居を訪れたのだろう。生来の品性と美貌を備えた多佳子が、この町角に佇んでいたのを想像すると、何とも言えぬ懐かしさが込み上げて来たに違いない。「辻小春」に多佳子への深い思いが籠められている。

木の葉髪撫でて別れの湯灌かな 山本まさみ

松田吉上の寸評
「湯灌」とは納棺する前に死体を清めることであるが、「湯灌」を詠った句に私は初めて接し、ハッとした。「木の葉髪」と「湯灌」。凄まじい取合せであるが、臨場感があり、句の完成度は高い。特に「木の葉髪撫でて」に静謐な悲しみと情が籠っている。掲句の様に、情と写生眼を大切にして句作を続ければ、俳句力は間違いなく伸びてゆく。


虚子の句には気を引く作品が多い。この句もその一つである。
地球の自転により銀河は西へ移動し、人々は逆に皆東へ移動する。しかし虚子は一人銀河と共に西へ行くのである。
博覧強記に基づく強い個性、揺るぎない自我が根底にあるこの一句。銀河イコール虚子という世界はどことなくアインシュタインの相対性理論を髣髴とさせる。悠然と銀河と共に西へ行くという気魄が見えてくる。虚子は常に世界の真の姿を追い求めたのだと思う。

丁度一年前思い立つことがあって私は京大俳句会の門を敲きました。図らずも京大生、京大教授、名誉教授と話す機会に恵まれ、目から鱗が落ちる心持の連続でした。名誉教授の御祖父がアインシュタインと親交があったのでその頃の話を聞かせて頂きました。アインシュタインは「もし自分が光と同じ速さで動いたら世界はどの様に見えるのだろうか」と考えたそうです。そこから相対性理論が生まれるのですが、時間が早く流れたり遅く流れたり、物質が動けば質量が増えたり、物が燃えると熱が発生したり、宇宙空間が湾曲したり、量子(コンピューター)が今日の電子(コンピューター)の一千倍もの速さで計算処理が出来るのはなぜ…、等々驚愕の真理が解き明かされる。
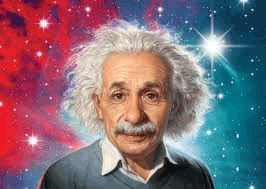
一方虚子の句にも真理を求めようとする気迫がそこかしこに見受けられる。
「紅梅の紅の通へる幹ならん」
「爛爛と昼の星見え菌生え」
「凍蝶の己が魂追うて飛ぶ」
等々です。
虚子の句が今も輝き続けているのは万象の真理を求めようとする心であり、揺るぎない自我が礎となっているからであろう。
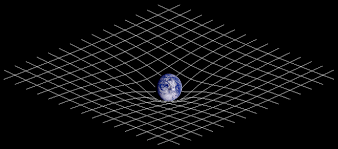
日々の生活の中に真理を希求する…大自然の中に真理を見出す。私はここに俳句の生命の根源があると思っている。
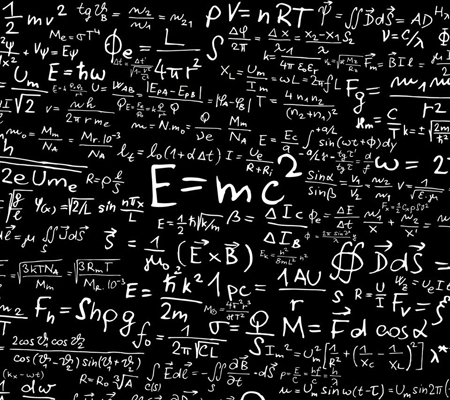
高木石子の一句鑑賞−句集「顕花」−

春の風邪忘るるほどに笑ひたり 石子
インフルエンザのように高熱でうなされるような症状ではなく、グズグズと風邪気味が続くような春の風邪。その風邪を忘れるほどのどんな面白いことがあったのだろうか。
想像する読み手も自然に笑みがこぼれる。大笑いの後はすっかり快復されたことだろう。
「病気を忘れる時、病気が治る」― 五木寛之―

Copyright(c)2019biohAllRightsReserved.